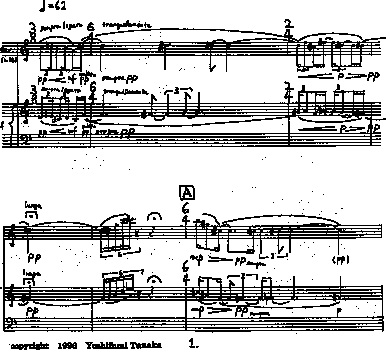
�@
�@
���̕��͂́A1999�N8���ɓ����ōs��ꂽ�u��ȃt�H�[�����v�ł̃v���[���e�[�V���������Ƃɍ쐬����A2000�N5���Ɂu��ȃt�H�[����'99�v�̋L�^���q�Ɏ��^����A���s���ꂽ�B����ȍ~�̎��̍�ȂɊւ���l�����́A���̕��͂����������Ƃ͕ω����Ă��Ă��邪�A�����ł͈�̋L�^�Ƃ��āA�Čf���邱�Ƃɂ����B�@
�T�v�@�܂��A�M�҂̍�Ȏ菇�ɂ��āA�������̍�i���ɂƂ�Ȃ�����������B���炩���߉��炩�̃V�X�e����ݒ肹���A��̓I�ȉ����I�ȑf�ނɊ�Â��č�Ȃ���邱�ƁA�܂����̍ہA���łɏ����ꂽ��������A�z����悤�ɂ��Č㑱���镔���������������邱�Ƃ��������B����ɁA��������Ƃɍ�Ȃɂ�����S�ʓI�ȊS�ɂ��ĉ�������B
�@
�@���y�����̍�ȉƂɂƂ��Ăǂ̂悤�ȑ��݂ł��邩���A�s�[�����Ă��̕��͂��n�߂�̂́A��̒�ł���Ƃ�����B�����ł́A���̍�ȉƂ������ɍۂ������v�z�������Ă��邩�����������B�������A���̍l�����͌����čۗ��������̂ł͂Ȃ��B�������ł�������������Ƃ���ŁA���܂܂ł���Ƃ����قǂ���Ԃ��ꂽ�����������Ԃ����ɂȂ邾�낤�B
�@���������A���y���ǂ̂悤�Ȃ��̂Ƃ��ĂƂ炦�邩�A�Ƃ������Ǝ��́A�����킸���̌��t�Œ[�I�Ɍ����\�킵������̂Ȃ̂��낤���H��q����悤�ɁA������Ȃ���ߒ��ł͌��t��_���ɂ���ĕ\���ł���悤�ȃV�X�e�}�e�B�b�N�Ȏ葱���͖w�ǂƂ��Ă��Ȃ��̂ŁA��Ȃ̉ߒ���]���Ƃ���Ȃ����t�ŕ\������ɂ͂��Ȃ�R�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ɂƂ��Ď����̉��y�����ł��邩�A���Ă݂鎖�͂ł��邩������Ȃ��B���y�͎v�z�\���̔}�̂ł͂Ȃ��B���y���̂���̎v�z�ł���ƌ����邩���m��Ȃ����A����͉��y�������ʂ̂��̂�\�����Ă���̂ł͂Ȃ��B�܂��A���炩�̌��I�ȃX�g�[���[��`�ʂ�����̂ł��Ȃ��B���y�ɂ���Đ�����Љ��ς�����Ƃ��v��Ȃ��B�Ƃ͂����A���y���A�܂�ʼn�X�̎v�f�Ƃ͑S���Ɨ��������R���ۂ̂悤�Ȃ��̂Ƃ��ĂƂ炦����A��i�̓����\����V�X�e�}�e�B�b�N�ȑ��ʁi��������邩�ǂ����͕ʂɂ��āj�����������肵�����Ƃ��l���Ă��Ȃ��B
�@�����ł͂ǂ�����č�Ȃ����邩�A�Ƃ����v�z�I�Ƃ������͂����ۓI�Ȗ�肩��b���n�߂�B����͌����Ď�����Ȃ̕��@�_�ɂ�������Ă��邽�߂ł͂Ȃ��B������i�������ۂ̍�ƍs���́A�Ȃ̃A�C�f�B�A�ɂ���Ă܂��܂��ł���A����̕��@���Ӑ}�I�ɗp���Ă���킯�ł͂Ȃ��B����͕��@�Ƃ������́A�P�Ɉ�̍�i���`���v���Z�X�ł����Ȃ��B�������A�ǂ̂悤�ɉ��y���������A�ǂ̂悤�ɂ��Ĉ�̍�i������čs���̂��A�Ƃ������Ƃ́A���ɓI�ɂ͂��̐l�����y���ǂ̂悤�ȑ��݂Ƒ����Ă��邩�Ƃ������ƂɌq�����Ă���͂��ł���B�����ł͎��̍ŋ߂̍�i�̂��������ǂ̂悤�ɔ��z����A�ǂ̂悤�ɏ��������߂�ꂽ�̂���U��Ԃ�A����ɂ������玄�����y���ǂ̂悤�ɂƂ炦�Ă��邩�A�����Ăǂ̂悤�ȉ��y����낤�Ƃ��Ă���̂��A�l���Ă݂鎖�ɂ�������1 �B
�@
�@��قǂ��q�ׂ��悤�ɁA���炩���ߌ��߂�ꂽ�菇�ɏ]���č�Ȃ��鎖�͖w�ǖ����̂ŁA��ʘ_�Ƃ��ďq�ׂ�͓̂���B�����A��Ȃ̍ۂɎc���ꂽ�X�P�b�`�≺�����A�����̗ނ���U��Ԃ��Ă݂�ƁA�����Č����A������Ȃ��J�n����i���邢�͂��̃A�C�f�B�A��j�̂́A�������ɋ�̓I�ȉ����I�ȃC���[�W�≹�y�I�Ȓf�Ёi�����ł͂������y�z�ƌĂԁj���v�������ɂ��鎖�������炵���B�v�����A�Ƃ����Ă�����͉����_��I�ȁu�슴�v�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B����͊��ɒm���Ă��鉽�炩�̉��y�I�Ȓf�ЁA��ۂɎc�鉹���Ȃǂ��v���o�����ɋɂ߂ċ߂��B�Ⴆ�A1997�N�ɏ�����17�t�҂̂��߂�linea-respiro��2 �̏ꍇ�A�ŏ��̃A�C�f�B�A�́A���̔N��2���A��q����Attributes II�̏������ŁA���̂Ƃ����܂��܂����ɂ���Maurizio Pisati����A�O�̔N��Niccol� Castiglioni���S���Ȃ����̂��������������������������B���̒m�点�����������A����Castiglioni�̂��߂�requiem�̂悤�Ȃ��̂���낤�ƍl�����B���̍�i�Ɏ�肩����ŏ��̉����I�ȃA�C�f�B�A�́ACastiglioni�̓����I�ȋ������܂˂����́i���Ȃ��Ƃ����̂���́j�ł������B����͂��̋Ȃ̌㔼�ɂłĂ��镔���ŁA�����̊y�킪�o���o���ɑf�����p�b�Z�[�W�����t���Ă��āA�����ɓ�l�̑Ŋy��t�҂ɂ��E�b�h�u���b�N�̃g�����������݂����Ƃ��������ł������B���ۂɂ��Ƃʼn��߂�Casiglioni�̍�i�������Ă݂�ƁA�ǂ�ɂ����̂悤�ȕ����͊܂܂�Ă��Ȃ������B���̋L���̕s���m�����A���̍�i�����炵�߂��ƌ����Ă��ǂ����낤�B���ǁA����������i��Castiglioni�Ƃ͎��Ă������Ȃ��ȂƂȂ�ACastiglioni�ւ�requiem�Ƃ����ŏ��̃A�C�f�B�A�͕�������Ă��܂����B
�@
�@1995�N����1996�N�ɂ����āA�A���g�T�b�N�X�ƃs�A�m�̂��߂�Attributes II��3 ����Ȃ����B���̍�i�ɒ��肷��܂ł̐��N�ԁA�Ƒt�Ȃ����������Ă����̂ŁA�����̊y����ǂ̂悤�Ɉ����悢���A�������t���Ȃ������B�����ł��̍�i�ł́A���ɈقȂ����G�����F���[�v�����Q�̊y����A����������̊y��Ƃ��Ĉ������ɂ����B�܂�A���F�̋ɂ߂ĈقȂ��̊y���g�ݍ��킹�āA��̐V�����y������A�Ƃ����̂��ŏ��̃A�C�f�B�A�ł������BFigure 1(a)�͂��̍�i�̖`�������ł���B�Q�̊y��͔����܂��͎l�������ꂽ�܂܁A��̐������Ȃ����čs���B���̐����̂�����̓����́A��r�I�����������ƁA��蓮���̏��Ȃ������Ƃ���ւ���A�Ƃ������Ƃł���B�Ȃ��i�s����ɂ�A�����̂Q�̕����͂��ꂼ��Ɨ��ɐV���Ȋy�z�ݏo���čs��(Figure 1(b))�B����ɂƂ��Ȃ��Ĉ�{�̎����قǂ��Ă䂭�悤�ɁA�s�A�m�ƃT�b�N�X�ō��ꂽ���̐V�����y��͏��X�ɉ�̂���A�ʂ̊y��ւƕʂ�Ă䂭�B
�@���̂悤�ɁA�����̊y���g�ݍ��킹�Ĉ�̊y��ƌ��Ȃ��A��̐������Ȃ���A�Ƃ����A�C�f�B�A�́A���̌㏑���ꂽ����̍�i�ŗp�����Ă���B�Ⴆ�ΑO�q��linea-respiro�ł́A�ŏ��̕����ł͈�̐����I�ȗv�f���A�l�X�Ȋy��̊ԂɎp����A���������������n������Ă䂭�B
�@
�@
�@
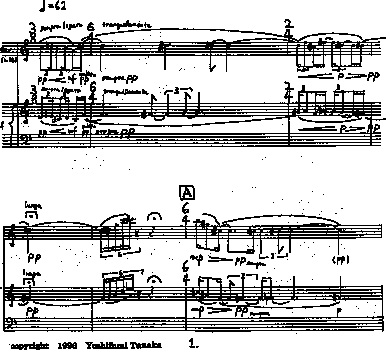
Figure 1(a)
�@
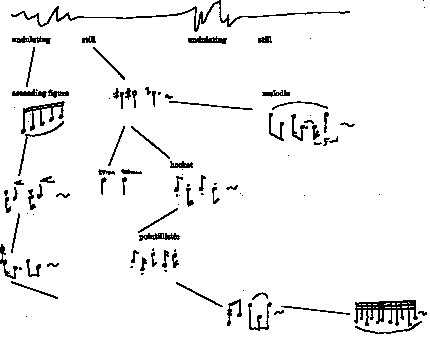
Figure1(b)
�@
�@Attributes II�ł́A��̐����̂��Q�̈ʑ��i���I�ȕ����ƐÓI�ȕ����j�����X�ɈقȂ����y�z���ĂыN�����悤�ɂ��ċȂ��i�s�����B���̃v���Z�X�͂��傤�ǐA�������X�Ɏ}���̂��A�������Ԃ�̌`������Ă䂭���ɂ����Ă���B�܂��A��X�����܂蕨���ɏW�������ڂ���ƍl���������Ă��鎞�̈ӎ���Ԃɂ��߂��B���̂悤�ȏ�Ԃł́A�z�N���ꂽ�l�X�ȃG�s�\�[�h���A���ʂȖړI��_���I��ѐ��Ȃ��Ȃ����čs���B������ɂ���A�����œ����I�Ǝv����̂́A��ȉߒ��̏o���_�ƂȂ���ɋ�̓I�Ȋy�z�Ɋ܂܂������̓������A���X�ɕʂ̊y�z�ւƌq�����čs���A�Ƃ������̘A�z�ߒ��ł���B��Ȃ̎�肩����ƂȂ�y�z�́A���̌セ�ꂪ�ǂ��u�W�J�v����邩���ʂ�������킯�ł͂Ȃ��A�ނ��낻�̊y�z�Ɋ܂܂��l�X�ȓ������A����ɕʂ̊y�z���Ăт��܂��čs�����Ƃɂ���Ĉ�̍�i�����ݏo�����B
�@�Ƃ���ŁA���������A�z�͔��ɒZ���f�ޒP�ʂōs����̂ł͂Ȃ��A������x�̎��������u���b�N��G�s�\�[�h���A������邱�Ƃō�i���\�������ꍇ������B�܂�A���炩���ߊ���̈قȂ����y�z������A�������Ȃ����킹��Ƃ��������ł���B����͑O�q��������ΐA���^�A���邢�͘A�z�^�̎菇�Ƃ͈���āA���傤�Lj�ՂŔ��@���ꂽ�j�Ђ����̒ق�����ߒ��Ɏ��Ă��邩���m��Ȃ��B�����ł͏ڂ����Ƃ肠���Ȃ����A�Ⴆ�Ό��y�l�d�t�̂��߂�fuggitivi(1996/7)��4 �͂��������u�����^�v�̗�ƌ�����Bfuggitivi�́A�����I�Ȋy�z���������̃u���b�N�̕��u�ɂ���Ă����Ă���B�����̃u���b�N�́A��s����u���b�N�Ɋ܂܂������ȉ��^���肪����ɐڑ�����Ă䂭�B
�@
�@�Ƃ͂����A���ۂɍ�Ȃ�����ۂɂ́A���̍�i���u�A�z�^�v���u�����^�v���m�ɋ�ʂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�u�A�z�v�I�Ȏ菇�Ɓu�����v�I�Ȏ菇�Ƃ͏�ɕs���Ɍ��т��Ă���B���̗�Ƃ���1998�N����1999�N�ɂ����č�Ȃ���6�y��̂��߂�����5 ���Ƃ肠����B
�@Figure2�́A���̍�i�̖`�������i���K�L��G�܂Łj��}���I�ɕ\���������̂ł���B���̕����͑S���łS�̓����I�ȃu���b�N���琬��A���ꂪ�ό^�����������������B�����̂S�̃u���b�N�ɂ͗l�X�ȗv�f���܂܂�邪�A���������X�g�A�b�v�����̂��AFigure3�ł���B�����̗v�f���ǂ̂悤�ȑ������܂�ł��邩�i���Y���̋K�����A�s�b�`�̖��m���A�s�b�`�̕ω������Ȃǁj�ɂ��ĕ��͂��s���A�e�v�f�Ԃ��ǂ̂悤�Ɋ֘A�Â����邩�����������B
�@���̍�i�̂�����̓����́i�s�K���ȁj���������p����Ă���_�ł���B��ɐG�ꂽlinea-respiro�ł́A�Ȃ̎��������ɒ����I�ł���A��̒��_���`������悤�Ȏ���������Ă����B����͂���Ӗ��Ŕ��ɌÓT�I�ȃf�B�X�R�[�X�ł���A���ł͂��������f�B�X�R�[�X��������x�����邽�߁A�s�K���Ȕ�������荞�BFigure 2�Ɏ������`�������ł��S�̃u���b�N�����Ȃ�̕ό^������������Ԃ���Ă���B���������傫�ȕω���������ꂽ��ł̔����́A���̍�i�̐����Ɍ�����B���������B���Ȕ����́A���ł�Attribute II�ɂ����Ă����I�ʑ��ƐÓI�ʑ��̌�ւƂ����`�Ō����Ă������A���̍�i�ł͂��O�ꂵ���`�ōs���Ă���B
�@
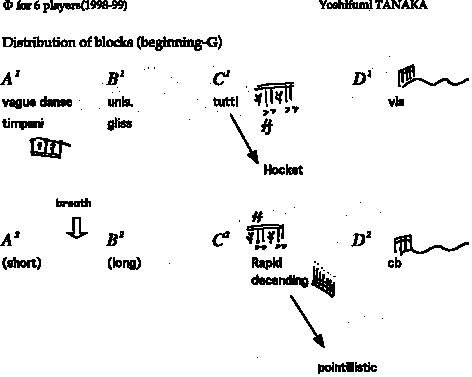
Figure 2
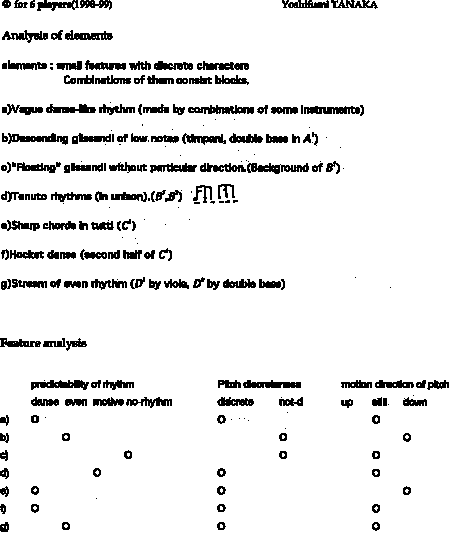
�@
Figure 3
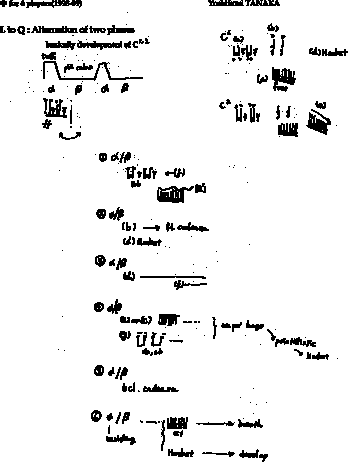
Figure 4
�@
Figure 4�̓��̌㔼�����̗�ł���B���̕����ł�tutti�ɂ�郊�Y�~�b�N�Ȓf��(a)�ƁA���ÓI�ȕ���(b)�Ƃ���ւł�����邪�Ab�ł�Figure 2�Ō����l�X�ȗv�f���g�ݍ��킹���Ă���B���̃��Y�~�b�N�Ȓf�Ђ́A�Ȃ̏I���߂��ŁA�S�y��ɂ��_���X���̕����ւƕϖe����B
�@
�@���Ō����悤�ɁA���ۂ̍�ȉߒ��ɂ����ẮA����܂łɏ������߂�ꂽ�f�ނ͂��邱�ƂŁA�㑱����������o���q���g�������鎖������B�������A�����ōs����u���́v���A�p�����g���b�N�Ȃ��̂ł͂Ȃ����ɒ��ӂ��Ăق����B�y�ȕ��͂ɉ����Ă͂����A���y���s�b�`�A�����A���F�ȂǂƂ������Ɨ��ȃp�����[�^�ɕ������Ă䂭���@�������B���������p�����g���b�N�ȕ����������Ȃ��鎖�ŁA�l�X�ȁu�g�ݍ��킹�v�̉\���͌����o�������̂́A�o���_�ɂ����������≹�y�I�ȑf�ނ̂����I�ȓ����͎�����B���������p�����g���b�N�ȕ��͂Ƃ͑ΏƓI�ɁA������Ȃɂ����Ă����Ȃ���Ƃ́A�X�̉�����f�ނ����S�̂Ƃ��Ă̎����A���I�ȓ������d�����A�����ɂǂ̂悤�Ȏ��I�ȓ������܂܂��̂��A���o���Č������邱�Ƃł���B���傤�ǁA���B�̖ڂ�����d���g�̓���̔g���Ƃ��Ċ������̂ł͂Ȃ��A���A�����A�Ȃǂ̐F�Ƃ��Ċ����Ƃ�̂Ɠ����悤�ɁA������Ȓ��ɍl������̂́A�o���o���ɕ������ꂽ�p�����[�^�ł͂Ȃ��A�l�X�ȃp�����[�^�����G�ɑg�ݍ��킳��鎖�Ő������ɂ߂ċ�̓I�ł���ȏ㕪�����悤�̂Ȃ���̑f�ނȂ̂ł���B���̂��Ƃ�Berio�̂����W�F�X�`���[�̊T�O��6�ɋ߂���������Ȃ��B
�@��̓I�Ȃ��̂���n�߂邱�ƁB�p�����g���b�N�ȕ��͂���ł͂Ȃ��A���̎��I�����A���邢�͕����̃p�����[�^�̑g�ݍ��킹�ɂ���Ăł������炩�̃W�F�X�`���[����A���y���n�߂邱�ƁB��̓I�ȑf�ނ͂����Ƃ́A�����ăs�b�`�≹���Ƃ������`���I�ȈӖ��ł̃p�����[�^�ɕ������鎖�ł͂Ȃ��A���̑f�ނ��A�ǂ̂悤�ɕω������邩�A�����Ăǂ̂悤�ɕʂ̑f�ނɌ��т��čs�����邩��T�鎖�ł���B
�@����������Ƃ𑱂��Ă���ƁA�i���X�g���郁�^�t�@�[�����j���y������������̐������ł���悤�Ɋ������鎖������B���傤�lj��|�Ƃ��̎}�Ԃ�����Ȃ���͂��݂����Ă䂭�悤�ɁA��Ȃ���Ƃ�����Ƃ́A���̉��y���ǂ��֍s���������A�ǂ��ɂ̂тčs���̂���ԗǂ����A�T���o�������̂悤�ɂ��v������7 �B
�@���̂悤�ɁA������Ȃ�����Ƃ��ɂ́A���炩���ߍ�i�̑S�̑��������Ă���킯�ł͂Ȃ��B��̓I�ȉ�������������ɘA��āA���ʓI�ɑS�̂��o���Ă���B����͗Ⴆ�A��̍זE�����A��̐��̂��`������Ƃ��A��܂��ȃv���O�����͂��łɈ�`�q�ɏ������܂�Ă��邪�A���ꂪ��̂ǂ�Ȃ��̂ɂȂ�̂��́A�������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����A���ꂪ�������鎞�ɋ��R�ւ��O�I�Ȋ��ɂ���Ă����E�����̂ƁA�����悤�Ȃ��̂��B
�@
�@��ɁA��Ȃ��Ă���Ɖ��y�͂܂�ň�̐����ł���悤�Ɋ�������A�Əq�ׂ��B���傤�ǁA�r�͓��̂ɂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�@�͖ڂ�艺�ɖ�����ΐ���Ȃ��悤�ɁA�߂͂���p�x�ȏ�ɋȂ���͂��������悤�ɁA���鋿���₠��v�f�́A������x�̎��R�͂��邯��ǂ��A��̂��̂�����ɂ����āA�ʂ̂ǂ�ƌq����̂���Ԃ悢�A�Ƃ�����ۂ������Ă���B�ł́A�Ȃ����̂悤�Ȉ�ہA���o�������Ă���̂��낤���H
�@���������Ɍq�����A���̌q�����́u�K�R���v�́A���̐l�̊w�K��o���ɂ���Đg�ɂ�����B���Ă��A�v���I���Ɍ��܂��Ă��āA�������牉㈂���Ă�����̂ł͂Ȃ����낤�B�ނ���A���ꂪ����Ɍq����Ƃ����o���𑽂����邱�Ƃɂ���āA���̌q���肪��莩�R�Ɋ�������悤�ɂȂ��Ă���̂ł��낤�B�ʂ̌�����������A���鉹�Ƃ��鉹���֘A�Â����Ē�������A�Ƃ������Ƃ��ꎩ�̂͊O�̐��E�ɑ��݂���̂ł͖����A�����܂ł���X�̐S���I�ȁA��ϓI�Ȑ��E�ł����Ȃ��A�ƌ������Ƃ��ł���B�������A����͌����ĊO�̐��E�Ƃ͖��W�ɁA�S�����R�ɐ�������o��A���邢�͖ϑz�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA������̂Ƃ�����̂̂Ȃ�������K�R�I�A���邢�͂�莩�R�ł���悤�Ɋ�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�������č����S�̂́A���ۂɑ��݂��鐶�����̂悤�ɁA�ǂ̂悤�ȍ\���ɂȂ�̂��A���ꂪ���m�ɋK�肳��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͖����B����͌����Ă݂�A�זE�̋����͉�X�l�ԂƓ��������A����ɂ���ďo���オ��S�̓I�Ȍ`�͐l�ԂƂɂĂ������Ȃ����m�̐����̂ł���\�������Ă���B
�@���y���������ł���Ƃ����Ƃ��A���y�͈�̗L�@�I�ȍ\�������A�Ƃ����ÓT�I�Ȍ�����z�N���������������낤�B�m���ɁA���Ō����悤�ȁA��̓I�ȑf�ނ͂��ēW�J���čs�����@�͂ǂ����u�u���[���X�I�v��8 �ƌ�����B�܂��A��ɏq�ׂ��悤�ȁu�f�ފԂ̎��R�Ȍq����v���o����ʂ��ė^������ȏ�A�ߋ��ɒ��������y�̉e�����犮�S�ɓ���邱�Ƃ͕s�\���낤�B�������A�f�ފԂ̌q���肪�u�L�@�I�v�ł������Ƃ��Ă��A����͗Ⴆ�x�[�g�[���F���̂悤�Ɋ������ꂽ��̕�����Ԃ��A�K���`������Ƃ͌���Ȃ��B�Ⴆ�x�[�g�[���F���̑�܌����Ȃ̑��y�͂̂悤�ɂ��������ȓ��@�����X�W�J����鎖�ɂ���č����̂́A��̌��S�Ȑ��E�ł���B����͊������A���B������I�Ȑ��E�Ōo������l�X�Ȏ����Ƃ͊u�₵�����̂��B�������A���͂��̂悤�ȕ������E����鎖�ɋ������Ȃ��B���̍�i�͂����Ζ��m�ȃN���C�}�b�N�X���`�����鎖�������āA����䂦���ɌÓT�I�ȖړI�I������z�N�����Ă��܂��������邪�A���ɂƂ��Ă͂��������ÓT�I�}���́A�P�ɗ��p����Ă��邾���ł��ꎩ�̂��ړI�Ȃ̂ł͂Ȃ��B�ꌩ�ÓT�I�Ȑ}���́A������̈ӎ����䂫�t���Ă����̂ɖ𗧂��A����ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��B
�@�ÓT�I�Ȍ`���́i������܂��ǂ����ł��������Ƃ̂����g�����j�_���I�Ȑ��_�ɂǂ������Ă���ƌ����邩������Ȃ��B���炩���ߖ��m�ȑO��Ɗ���̖��肪�^�����A��������_���I�Ȑ��_�����鎞�A��X�͂�������ԈႦ�Ȃ��悤�ɐ_�o���点�A���̂��ƂɈӎ����W������B�����đO��Ɩ����̂Ȃ��A�����Ȍ��_���o���Ă���B����Ɠ����悤�ɁA��܌����ȑ��y�͂ł̃x�[�g�[���F���̓��]�́A�`���̓��@�����т����_���I�Ŗ����ȑS�̂��o���Ă���B�������A��X�́A��ɉ����ɏW�����A��̎��ɂ����ӎ��������Ă���킯�ł͂Ȃ��B����̎��ɂ��čl���Ȃ���ΐ���Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A��X�̈ӎ��͂ǂ��������Ă���̂��낤�B���邢�́A��������̎����ɂ��ē��_���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����F�l�Ƃ�������y����ł��鎞�A�b��͂ǂ��ڂ��Ă䂭�̂��낤���H
�@����̈Ӑ}�������Ȃ��A�z�A�C�܂܂ȉ�b�͂����Όォ��H��Ȃ������Ƃ��o���Ȃ������肷��B�ܘ_�A�ǂ�Șb�肾�����̂��A������肪����ɂ��čč\�����Ă݂悤�Ƃ��邱�Ƃ͂ł���B�ł��A��b���Ă���ԁA�ˑR�N�����˔��q���Ȃ����Ƃ������o���āA����ŋ}�ɘb�肪�ς�����̂����m��Ȃ��B���邢�͓ˑR�ڂɓ�����������̂��A����܂łɍl���Ă���������S���Ⴄ���̂ɂ��Ă��܂��������m��Ȃ��B�A�z�����R��b���A��X�͂������R�ɖ����s���Ă���B�Ȃ̂ɁA���ꂪ�ς�A���ꂪ�Ȃ����̂��킩��Ȃ��Ȃ�B��X�͂��ꂪ���Ȃ̂��m��Ȃ��B�����������ɁA������s���Ă���̂����瓖�R�m���Ă���͂��Ȃ̂��B
�@���̂��Ƃ́A���̍�Ȃ̎菇�i�����Ă��̕��͂Ƃ��j�Ƃǂ������Ă���B����������̂���͂��߂�B���ꂪ���R�ɐi�ނɔC����B����u�ԁA���ƂȂ���b����������݂����ɁA�Ȃ��I���B���͉��y�ł�����o�������̂����m��Ȃ��B�m���Ă���̂ɒm��Ȃ����Ƃ����o�����ƁB�u�����łȂ���ΐ���Ȃ��S�́v��ڎw���̂ł͂Ȃ��A���ꂪ���R�ɐi�݁A���ꂪ�������������Ɍ����킹��B���̃v���Z�X���A���ۂɕ�������Ă��邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B��̕������E���o����̂ł͂Ȃ��A�����Ȃ��琢�E�̐V�������ʂ������Ă���悤�Ȃ��́B���傤�NjC�܂܂Ȃ�����ׂ肪���X�ƐV���ȓW�J�����čs���悤�ɁB
�@
�@���̂悤�ɏ����Ă���ƁA���͂ǂ������y�̎��ԓI�ȓW�J�ɂƂĂ�����������炵�����ƂɋC�Â��B�f�ނ������ɏ������Ă䂭���A�Ƃ������́A���y�̎��ԓI�ȓW�J�̖��ł�����B�����������Ƃ������Ԃ����݂��Ȃ�����ꎩ�̂����݂����Ȃ����̂����f�B�A�Ƃ��鉹�y����A���Ԃ���苎�邱�Ƃ͕s�\�ł���A���y���������Ƃ́A���Ԃɂ��Ă̔��ȂȂ����Đ��藧�����Ȃ��B
�@�c�_�m�ɂ��邽�߂ɁA�����Ęb��P�������āA���y�̎��ԓI�W�J�̃p�^�[���Ɋւ��ē�̑�\�I�ȗތ^���l���悤�B��́A����f�ނ����̗L�@�I�ŖړI�I�Ȏ��������o���A�Ƃ����`���I�ȃh���}�g�D���M�[�ł���A�I�y���₢����`�ʉ��y�Ɍ�����悤�ȉ��炩�̃X�g�[���[�����邩�ۂ��Ɋւ�炸�A���������I�̐��m���y�ɂ����Ĕ��ɍL��������W�J�ł���iLachenmann��Ferneyhough����O�ł͂Ȃ��j�B������́A���Ƃ���Cage�ɑ�\�����悤�ȁA�X�̉��̔����������邽�߂Ɂu�f�ނ����ԓI�ɓW�J����v�Ƃ����l������������闧��ł���B���̗���ł͉��y�̎��ԓI�ȓW�J�r������A���Ɍ��肳�ꂽ���f�ނ����u���ꂽ�A����Ζ����ԓI�ȏ�Ԃ��u�������B
�@�����g�͍ŏ��ɏq�ׂ��悤�ɁA���ʼn����ʂ̂��̂�\�����悤�Ƃ͎v��Ȃ��B�]���ĉ��y�ʼn��炩�̃X�g�[���[�i�����h���}�ł���R���f�B�ł���j��\�����邱�Ƃɂ͋������Ȃ��B����A�u�X�̉��̔������v�͌��ǎ��܂��ǂ��ł��̌��ł���B��������ł����̒����特��I�ю��A���������̉������ʂ��A������x�Ɨ��������̂Ƃ���i���ꂪ�܂��ɍ�ȂƂ������ƂȂ̂����j�̂Ȃ�A��͂肻���ɂ͎��ԂƂ������́A���Ԃ̒��ɂ����ɉ��������Ă䂭�̂��A�Ƃ�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B��ɏq�ׂ��Q�Ԗڂ̗���́A�����郈�[���b�p�I�Ȕ��w�����z��������Ƃ������葁�����@�ł��낤���A���ɑ����̍�ȉƂ�����������i�݂����Ă���B��������ȏ�͂���Ȃ��A�Ƃ������炢���B���͂����Ă��̗���ɗ��K�v�͂Ȃ����낤�B�Ȃ��Ȃ玄��肤�܂����̃A�C�f�B�A����������l����R���邩�炾�B�Ƃ͂����A�`���I�ȃh���}�g�D���M�[�ɖ߂�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���Ԃ͂��̂ǂ���ł��Ȃ��Ƃ����T���Ă���̂��B����͂��Ƃ��\�z�����ڍ��ɂ���Č`������鎞�Ԃł���A���������U�킵�Ă䂭�^���A�Ƃł�������B�A�z�⎩�R��b�ɂ́A�����͂����Ă��ړI�͂Ȃ��B���Ƃ����Ė��W�Ȃ��̂��P�ɕ���ł���̂ł��Ȃ��B����͉��炩�̌��_��ڎw���ē˂��i�ނ��̂ł͂Ȃ��A��Ɉڂ낢�g�U���Ă䂭�B���̈Ӗ��ŁA�A�z�⎩�R��b�͎��̒T���Ă��鉹�y�̎��ԓI�ȓW�J�̈�̃��f���Ƃ����邾�낤�B
(2000�N5��)�@
�@
�@
��1 ���炩���߂��f�肵�Ă��������̂́A�ȉ��̋c�_�ł͘b���킩��₷�����邽�߂ɐ����ł��Ȃ�ɒ[�Ȑ}�������s���Ă���A�Ƃ������Ƃł���B���������P�����ɂ���Č��߂�����Ă��܂��P�[�X�����邱�Ƃ��Y��Ă͂��Ȃ����Ƃ��A���炩���߂������������������B
��2 �H�g�䍑��20���I���y�Z�~�i�[&�t�F�X�e�B���@���̈Ϗ��ō�Ȃ���A1997�N8����Johannes Kalitzke�w��Klangforum Wien�ɂ���ď������ꂽ�B
��3 �T�N�\�t�H�[���t�҂��V���M�u���̈Ϗ��ō�Ȃ���A1997�N�̂Q���ɏ������ꂽ�B
��4 1996�N8���ɏH�g��Z�~�i�[�ŏ�������A�H�g���ȏ܂������A���N�����ł����ꂽ�B
��5 Beethovenhaus Kammermusiksaal(Bonn)�̏\���N�̂��߂ɈϏ�����A1999�N��Bonn��Jurjen Hempel�w��Ensemble Musikfabrik�ɂ���ď������ꂽ�B
��6 Osmond-Smith,David, Berio (Oxford,New York, 1991). [�������Ŗ� �x���I �y��, 1998.]
��7 �������u���R�ɂ�������v�Ȃ��������ɂ�����邱�Ƃɂ͔��ɑ傫�Ȋ댯������B�����ł͐[���c�_���Ȃ����A��q����悤�Ɂu���R�ɂ�������v���Ƃ̔w��ɂ͒�����i���邢�͏�����j�̉ߋ��o����K���Ɉˑ�����B���̂��߁u���R�ɂ�������v���Ƃւ̌Ŏ��́A���肫����̂��̂������ݏo�����Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��̂ł���B
��8 �v���[���e�[�V�����ł̋ߓ������̎w�E�B